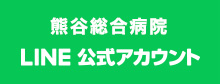- 脳神経外科とは
- 当院脳神経外科の特色
- 診療内容
- 代表的疾患の年間手術数
- トピックス
- 脳卒中センター/SCU(脳卒中集中治療室)開設(2021年7月)
- 脳動脈瘤の治療
- 脳磁図検査(MEG検査)
- 医師紹介
脳神経外科とは
脳神経外科は、中枢神経(脳、脊髄)すべての神経系に関する疾患を診療する外科です。 新生児から高齢者までを対象としており、年齢による制限はありません。
当院脳神経外科の特色
24時間、積極的に救急患者様を受け入れ治療を行っています。最新の診断技術、最先端の治療技術で治療を行うことを基本にしています。特に脳血管疾患(くも膜下出血、未破裂脳動脈瘤、脳梗塞)、脳腫瘍、水頭症の治療に力を注いでいます。中枢神経の病気は、合併症があることが多いのですが、当院は総合病院であるため、他科との連携により全身状態の把握ができる利点があります。
診療内容
脳腫瘍
神経膠腫、髄膜腫、神経鞘腫、下垂体腺腫、転移性脳腫瘍など
脳血管疾患
破裂脳動脈瘤、未破裂脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳出血、脳梗塞など
脊椎脊髄外科疾患(頚椎領域)
変形性頚椎症、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、脊髄空洞症など
機能神経外科疾患
顔面けいれん、三叉神経痛、パーキンソン病など
神経外傷
脳挫傷、慢性硬膜下血腫
その他
認知症(アルツハイマー病、正常圧水頭症等による)、てんかん
代表的疾患の年間手術数
| Kコード | 手術名称 | 2021年 | 2022年 | 適応疾患例 |
|---|---|---|---|---|
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 5 | 髄膜腫、血管腫、脳動静脈奇形など | |
| K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 9 | 後大脳動脈狭窄、小脳動脈狭窄 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 7 | 11 | 内頚動脈狭窄症 |
| K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 5 | 慢性動脈閉塞症(四肢、腸骨動脈、内頚動脈など) | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 19 | 7 | 脳血栓 |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 5 | 9 | 脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳腫瘍など |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 15 | 7 | 脳動脈瘤 |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 25 | 25 | 水頭症 |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 7 | 12 | 脳腫瘍、神経膠腫など |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 17 | 17 | 急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、慢性硬膜下出血、脳挫傷など |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 36 | 33 | 慢性硬膜下血腫 |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 9 | 7 | 急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、慢性硬膜下出血、脳内血腫など |
| K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | 6 | 水頭症、髄膜炎、脳室内出血など | |
| K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 (多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 |
6 | 7 | 脊柱管狭窄症、頚椎症性脊髄症など |
トピックス
ブレインアタック
脳卒中の死亡率はがん、心疾患についで第三位と多く、近年脳出血より脳梗塞が増えています。最近脳梗塞に対し発症3時間以内に適切な治療(t-PA)を行うことの重要性が強調されています。そこで心臓発作(ハートアタック)と同様に緊急処置が必要な病気と認識され、ブレインアタックと呼ばれるようになりました。
- 身体の片側の顔、手、足に突然脱力、しびれがおこる。
- 突然片目が見えにくくなったり、ものがぼやけて見える。
- 言葉が急にしゃべりにくくなったり、理解できなくなる。
- 突然のめまい、ふらつき、転倒
このような症状がありましたら、すぐに当科受診をしてください。
脳卒中センター/SCU(脳卒中集中治療室)開設(2021年7月)
SCUとは?
SCU(Stroke Care Unit:脳卒中集中治療室)とは、脳卒中を起こして間もない期間、病態が不安定な脳卒中患者さんに対して、効率的な初期治療を行う病室のことです。
2015年に発表された脳卒中治療ガイドライン(日本脳卒中学会)では、SCUで治療することにより、死亡率および再発率の低下、入院期間の短縮、自宅退院率の増加、長期的な日常生活動作と生活の質の改善を図ることができると、明記されています。
当院のSCUの特色
1. 24時間受入れ体制
脳卒中治療においては、t-PA静注療法等の内科的治療、血栓回収術等の血管内治療、血腫除去術等の外科的治療など、一刻を争う迅速な対応が必要となります。
当院では、脳神経外科医が24時間常駐し、脳卒中ホットライン体制により、病状に応じて救急隊や医療機関から患者の受け入れに対応致します。
2. チーム医療
当院では、脳卒中の専門医師を中心に、脳神経外科医、看護師、リハビリスタッフ、MSWで構成された脳卒中チームで治療に臨んでおります。毎朝のカンファレンスにて治療方針の確認と決定、情報共有を随時行い、各職種が迅速に介入することにより、治療内容の向上に努めます。
3. 超早期リハビリテーション
入院当日または翌日という超早期からリハビリテーションを開始し、早期離床を進めてまいります。また、嚥下障害のある症例では、嚥下評価を行うなど、誤嚥のリスクを最小限にしつつ、早期に経口摂取を開始できるように取り組んでいきます。
対応可能な疾患
急性期の脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など) など
- 脳に栄養や酸素供給する血管が閉塞し、その領域がダメージを受ける脳梗塞
- 脳の血管が高血圧等で破れることで生じた血腫が脳にダメージを与える脳出血
- 脳の血管に動脈瘤という瘤(こぶ)ができ、ここから出血するくも膜下出血
現在、血管の閉塞による脳梗塞では、血栓を溶かす薬による点滴治療(血栓溶解療法)のほか、血管にカテーテルを通して血管を拡張したり血栓を除去したりする治療(血管内治療)が、状態に応じて施行可能です。
当院は、埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク(SSN)の基幹病院であり、24時間血栓回収治療が可能な医療機関として消防機関との連携も行っております。
地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟との連携
脳卒中の場合、急性期治療は概ね1~2週間で終了しますが、その後も障害が残ることが多く、引き続きリハビリテーションが必要です。そのような場合、当院では地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟を併設しており、他院へと転院することなく院内で継続したリハビリテーションを行うことが可能です。
埼玉県急性期脳梗塞ネットワーク(SSN)について
当院は、埼玉県急性期脳梗塞ネットワーク(SSN)の基幹型病院です。
埼玉県急性期脳梗塞ネットワークとは、急性期脳梗塞の疑いがある傷病者に対し、専門的治療が可能な医療機関を消防機関が迅速に選定・搬送するための埼玉県独自の連携システムです。(消防法第35条の5第2項第6号)
超急性期脳梗塞に対しては、その適応を慎重に判断し以下の治療を行います。
- 血栓溶解療法:強力な血栓溶解薬(rt-PA)を静脈投与し、脳梗塞の原因となる血栓を溶解する
- 血栓回収療法:カテーテルにより脳血栓を直接回収し、脳血流の再開通を図る
この血栓溶解療法(rt-PA)および血栓回収療法が常時または随時実施可能な医療機関を「基幹病院」と呼び、血栓溶解療法のみ実施可能な医療機関を「連携病院」と呼びます。
当院は、24時間体制で超急性期治療が提供可能な体制を整備しており、埼玉県急性期脳梗塞ネットワークにおける「基幹病院」としてその役割を果たしております。
脳動脈瘤の治療
当院では脳動脈瘤の治療は、クリッピングを原則にしています。動脈瘤の大きさ、場所年齢、全身状態により血管内治療を行っています。血管内治療は専門医に依頼していますので、当院ですべての脳動脈瘤の治療に対処可能です。